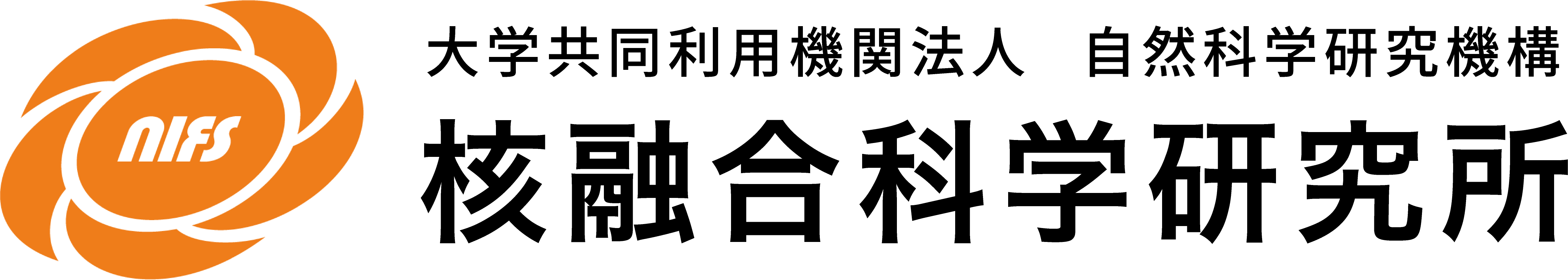新着情報
- プラズマ量子プロセス
- お知らせ
第15回プラズマ量子プロセスユニットセミナー「格子QCDを用いたQCDの非摂動シミュレーションの現状について」
核融合科学研究所(NIFS)プラズマ量子プロセス(PQP)ユニットでは、ユニットの研究活動を広く発信していくために、セミナーを開催しております。今回は、講師として広島大学の石川健一先生をお招きして「格子QCDを用いたQCDの非摂動シミュレーションの現状について」と題してご講演いただきます。石川先生は、素粒子物理学が御専門です。
本講演は、ネットワーク型研究加速事業の課題「多階層現象の複合大域シミュレーション研究拠点の構築」と連携しています。
【実施要項】
題目:格子QCDを用いたQCDの非摂動シミュレーションの現状について
講師:石川 健一(広島大学大学院先進理工系科学研究科 准教授)
日時:2025年3月6日(木)10:45-12:00
会場:核融合科学研究所 研究1期棟 5階501号室 ※ハイブリッド開催
【概要】
プラズマ中でイオン(H+)と電子の質量に約2000倍の差があることは疑問なく受け入れられているが、この質量の差の理由は何だろうか?
陽子の質量や核力のポテンシャルが理論的に計算できるようになったのは意外にも最近であり、1990〜2000年代になってからといえる。その方法は格子QCDと呼ばれるもので、ゲージ対称性の原理から理論的に計算される。
量子色力学(Quantum Chromodynamcs, QCD)は、陽子や中性子、パイ中間子などのハドロンの性質を、それらの構成要素と考えられているクォークやグルーオン*1 と呼ばれる粒子の量子力学で説明する理論である。このQCD理論の基礎方程式は相対論的電磁気学における電子と電磁場の基礎方程式とほぼ同じ形をしているが、電磁気の電荷に対応する自由度*2 であるU(1)ゲージ対称性*3 が、より一般的な SU(3)ゲージ対称性*4 に拡張されている。この拡張によりクォークは色電荷というものを帯びており、さらにグルーオンも色電荷を帯びているため、基礎方程式は非線形な方程式となっている。この理論を量子力学的に取り扱えるようにしたものがQCDである。
QCDではクォークとグルーオンの相互作用(色電荷結合定数)が高エネルギー領域では小さくなる「漸近自由性」という性質を持つ*5。このためQCDの摂動近似計算による計算がハドロンの高エネルギー散乱実験に対して有効であり、そこではQCDの正しさが確認されている。一方、低エネルギー領域では色電荷結合定数は大きくなるため、QCDの摂動近似計算から陽子や中性子の質量を評価することはできない。格子QCDは、QCDを4次元時空の規則格子の上で定義した理論であり、数値計算により摂動近似ではない計算を行う手法である。陽子や中性子の質量をQCDの原理(ゲージ対称性)から計算できる、現在我々が知っている唯一の計算手法である。
本講演では、QCDの概観とこれまでになされている格子QCD計算の一部を説明し、格子QCDのシミュレーション技法とともに、スーパーコンピューターの技術や利用の観点や格子QCD計算で用いられている技法の発展応用性についても紹介したい。
【注釈】
*1 グルーオン:強い相互作用(核力の起源になる力)を伝える粒子。電磁気での光子に相当。
*2 電荷に対応する自由度:電子の場の持つ複素数の位相の自由度。
*3 U(1)ゲージ対称性:U(1) は 1次のユニタリ群のことで e^(iθ) である。これにより変換しても電磁場が変わらないとすることからマックスウェル方程式が導かれる。
*4 SU(3)ゲージ対称性:SU(3) は 3次の特殊ユニタリ群であり、3行3列のユニタリ行列で構成される(「特殊」は行列式が1)。
*5 相互作用が高エネルギー領域では小さくなる:陽子や中性子の大きさよりも小さな領域(= 1 GeV以上の高エネルギー)では力が弱くなる。
【用語説明】
・クォーク:アップ(u)、ダウン(d)、ストレンジ(s)、チャーム(c)、ボトム(b または ビューティ)、トップ(t)の6つのフレーバー(種別の名称)があり、陽子は uud、中性子は udd から構成される。単独の u や d の質量は 2~5 MeV 程度であり、陽子の質量(~1 GeV)よりもかなり小さい。
・レプトン:電子とニュートリノの仲間たち。電子、ミュー粒子、タウ粒子、電子ニュートリノ、ミューニュートリノ、タウニュートリノ。
・ハドロン:陽子、中性子や中間子などのこと。
・場の量子論:電磁場のような場を量子化した理論一般を場の量子論という。
・素粒子標準模型(標準模型):素粒子物理学における物質と物質間に働く相互作用を記述する、相対論的場の理論の現在知られている実験的に確立した模型。ヒッグス粒子が観測されたことで、標準模型の大枠の正しさが確認された。この理論は、電磁気力、弱い力、強い力の3つの相互作用とそれらを感じる物質粒子をミクロな自由度で記述する。
・ゲージ原理:電磁気学においては、電子の場が持っている複素位相(複素平面)が宇宙全体で統一的に絶対基準が決まらないようになっているべきであるという相対性原理を適用すると、自然と電磁場(4元ベクトル・ポテンシャル)の自由度が必要となる。この自由度が出てくる仕組みは複素位相の数学的性質からU(1)ゲージ対称性を理論が持つべしという要請に対応する。さらに、ゲージ対称性を要請すると、物質と力の媒介粒子の相互作用の形まで決まってしまう。このような、ゲージ対称性に基づいて相互作用と力の媒介粒子を決める原理をゲージ原理という。
・格子場の理論、格子QCD:場の量子論をファインマンによる経路積分量子化を通じて数値積分できるように、格子化(離散化)された時空上で定義した場の量子理論。4次元時空の実時間座標をユークリッド化(純虚数化)することで、格子場の経路積分はモンテカルロ積分法で数値計算できる離散自由度の多重積分となる。格子QCDはモンテカルロ積分法を用いてQCDに関する物理量の基底状態近辺の期待値を計算・評価する。
【連絡先(世話人)】
舟場久芳:funaba.hisamichi(at)nifs.ac.jp
※(at) を@に直してください。