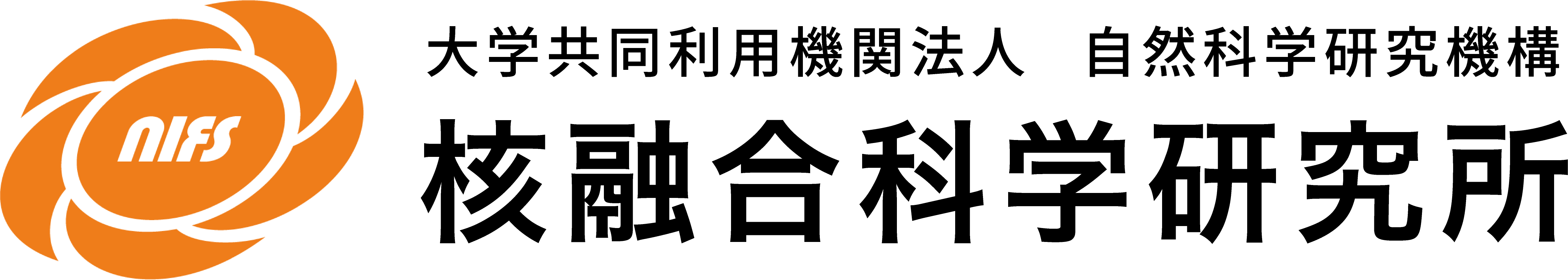新着情報
- プラズマ量子プロセス
- お知らせ
第19回プラズマ量子プロセスユニットセミナー “クォーク・グルーオンプラズマの物理とその周辺”
核融合科学研究所(NIFS)プラズマ量子プロセス(PQP)ユニットでは、ユニットの研究活動を広く発信していくために、セミナーを開催しております。今回は、講師として広島大学の野中千穂先生をお招きして「クォーク・グルーオンプラズマの物理とその周辺」と題してご講演いただきます。
野中先生は、原子核物理・ハドロン物理学が御専門です。
【実施要項】
題目:クォーク・グルーオンプラズマの物理とその周辺
講師:野中 千穂(広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授)
日時:2025年8月5日(火)
16:00-17:15 (ハイブリッド開催)
会場:核融合科学研究所 研究1期棟5階501号室 および Zoom
*Zoom参加については別途、案内のメールをお送りします。
【概要】
クォークやグルーオンの新しい物質クォーク・グルーオン プラズマ(QGP, おおよそ200MeV 以上の温度で実現するとされる)の解明を目指し、実験と理論の双方から世界規模の研究が行われている。通常、クォークやグルーオンはハドロン(※)の中に閉じ込められている。しかし、高温・高密度では量子色力学(QCD)の漸近的自由性により閉じ込められていたクォークやグルーオンが飛び出し自由ガスのように振る舞う。QCD相転移の実験的検証を目標にリトルバンとも呼ばれる高エネルギー原子核衝突実験が1970 年代より開始し、2005 年には遂に、米国・ブルックヘブン国立研究所(BNL)のRelativistic Heavy Ion Collider(RHIC)でQGP生成に成功した。ところがこのQGPは強結合QGP(流体的)であり、これまでの弱結合QGP(気体のように振る舞う)の予想を覆す衝撃の結果であった。さらに、2010年の CERN の Large Hadron Collider(LHC)におけるRHICよりも衝突エネルギーが10倍以上も高い実験の開始、RHIC における衝突ビーム・エネルギー走査実験、sPHENIX(※※)と精力的な実験が続いている。LHC でのさらなる高エネルギー原子核衝突実験の続行とともに、2035年の EIC(※※※)実験開始もあり、世界規模でのさまざまな研究の進展と可能性がある。
QGP物理のおもしろさと難しさは直接クォークやグルーオンを観測することができないことにある。そのため実験やその背景にある物理の理解には理論からの説明や解釈が必要となる。また実験に生じる粒子の生成過程や時空発展のダイナミクスを記述する必要がある。
現在、標準的な模型になっているのは、相対論的流体模型である。さらに衝突後に存在すると考えられている磁場を考慮に入れた相対論的抵抗性電磁流体の開発もされている。ここでは、時空発展のダイナミクスに関連した物理、相対論的流体模型を取り上げ、周辺物理との関連性を議論する。
※) 陽子や中性子などのこと
※※) ブルックヘブン国立研究所の粒子検出器
※※※) ブルックヘブン国立研究所の「電子-イオン衝突型加速器」計画
講演の翌日 8月6日(水)10:00 から同会場(研究1期棟5階501号室およびZoom)において、野中先生との研究協力についての打合せを行う予定ですので、こちらにもぜひ御参加ください。
本講演は、ネットワーク型研究加速事業の課題「多階層現象の複合大域シミュレーション研究拠点の構築」と連携しています。
【講演資料】
講演資料はこちらからご覧いただけます。
【連絡先】
舟場久芳:funaba.hisamichi(at)nifs.ac.jp
※(at) を@に直してください。